 濱嘉之
濱嘉之  濱嘉之
濱嘉之  濱嘉之
濱嘉之 IT捜査と京大卒ヤクザが激突──濱嘉之『警視庁公安部・青山望 頂上決戦』で見える裏社会の闇
 濱嘉之
濱嘉之 【書評】濱嘉之『警視庁公安部・青山望 巨悪利権』|半グレ・ヤクザ・極左・中国の全てがトリカブトで繋がるシリーズ最高傑作
 濱嘉之
濱嘉之 濱嘉之『警視庁公安部・青山望 濁流資金』:次々起こる怪事件!暗号資産をめぐる巨悪と公安警察の戦い
 濱嘉之
濱嘉之 濱嘉之『警視庁公安部・青山望 機密漏洩』モデルは岸田文雄?中国の闇に迫るリアルな警察小説
 久坂部羊
久坂部羊 【書評】久坂部羊『人はどう死ぬのか 人生の予習』――医師が語る「死に方」のリアルと生き方へのヒント
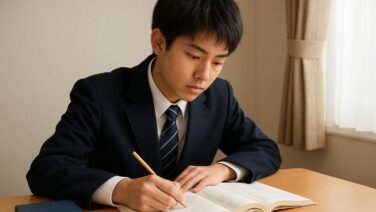 帝国書院
帝国書院 【書評】『世界史図説タペストリー』(帝国書院)はなぜ最強の教養書なのか?|大人がハマる「見る世界史」で小説やニュースが10倍面白くなる!
 小笠原弘
小笠原弘 小笠原弘幸「オスマン帝国は、いかに『中世』を終わらせたか」|第一人者が語る1453年の衝撃と近代への転換
 塩野七生
塩野七生 【書評】『レパントの海戦』が描く歴史の皮肉|キリスト教世界はなぜ勝利し、それを活かせなかったのか?
 塩野七生
塩野七生 【書評】『ロードス島攻防記』圧倒的物量で迫るオスマン帝国と、聖ヨハネ騎士団の凄絶な戦い
 塩野七生
塩野七生 